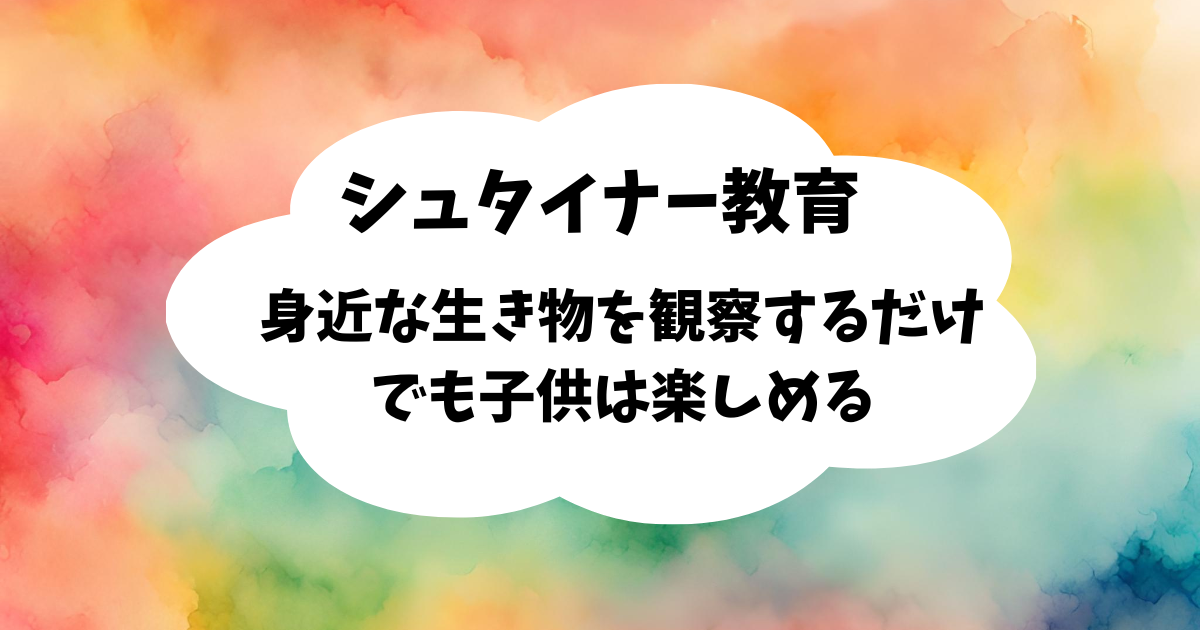
こんにちは、はりねです。
今回は「身近な生き物を観察するだけでも子供は楽しめる」というテーマでお話ししたいと思います。
子供と観察した身近な生き物たち
身近な生き物には、小さな子供でも安全に観察できる昆虫がたくさんいます。例えばアリ、ダンゴムシ、てんとう虫、ちょうちょなど、近所の公園や庭で簡単に見つけることができますよね。
シュタイナー教育では「自身で体験する」ことを重要視しています。実際に触れることで、子供たちはその生き物がどんな形や感触をしているのか、自分自身で感じ取ることができます。アリを手に取って触ってみたり、ダンゴムシが丸くなる様子を間近で観察したりすることで、子供たちは生き物に対する興味や好奇心を育てることができるんです。
アリの巣に砂を入れてみた🐜💦
先日、息子と従兄妹の子供たちで一緒にアリの巣を見つけました。子供たちは興味津々で巣に砂を入れてしまい、巣が埋まってしまったのですが、翌日再び見に行くとアリたちは見事に穴を復旧していました。それを見た子供たちはとても驚いていました。
アリってすごいね!また巣を作り直している!
このように実際に自分たちで観察して発見することで、生き物たちの驚くべき能力やたくましさに気づきます。そしてその気づきが、新たな興味や探究心を生み出すんですよね。

ダンゴムシやてんとう虫を触ってみよう
ダンゴムシやてんとう虫も子供たちにとって素晴らしい観察対象です。ダンゴムシは手で触るとクルッと丸くなる姿が面白く、てんとう虫は赤や黒の模様が美しいので、子供たちの興味を引きます。
それぞれの昆虫に独特の形や動きがあり、触れることでその感触も体験できます。「ダンゴムシは丸くなるんだね」「てんとう虫の模様がかわいいね」など、子供たちが自分の言葉で発見を表現する姿に、親としても喜びを感じます。
直接触れてその感触や動きから知識を得ることが大切
シュタイナー教育では、0歳~7歳の幼少期は身体づくりが優先とされ、なるべく頭を使わないように親たちは心掛けることが必要とされています。生き物の観察も、図鑑や知識だけで学ぶのではなく、直接触れてその感触や動きから知識を得ることが大切です。
特にこの時期は「素語」と呼ばれる、物語を親が直接語る方法で伝えることも推奨されています。「アリがどうやって巣を作り直すか」「てんとう虫はどうやって空を飛ぶのか」など、親が実際に観察した経験を子供たちに伝えながら、生き物たちの物語を作って話すことで、子供たちの興味をさらに引き出すことができますね。
まとめ
子供たちと一緒に身近な生き物を観察することで、その自然の美しさや不思議さに気づくことができます。シュタイナー教育の「自身で体験する」を実践しながら、ぜひお子さんと一緒に生き物の世界を探究してみてくださいね!
それでは、またお会いしましょう😊
↓どれか一つクリックしていただけると励みになります😊